
久礼波(くれは)は不思議な男だった。
半年ばかり前にふらりと美濃を訪れて、いつのまにか居着いた。
あまり人付き合いが得意な性格ではないらしいが、含羞の笑みに人の良さが伺い知れた。
美濃の人々の農作業を手伝ううちに、人々は彼の特異な才能を知った。
久礼波は土木に関する専門的な知識と技術を持っていた。
井戸を掘り、堤防を築き、用水路を整備し、道路を整える。
彼のおかげで生活の不安や不便が随分改善され、美濃の人々は彼に感謝したし、
久礼波の方もすっかり美濃の生活に馴染んだ。
いつのころからか、久礼波のそばで親し気に語らう沙那女(さなめ)の姿が見られるようになった。
つい最近、母を亡くした沙那女は久礼波と語らうたびにその悲しみが癒されていくのを知った。
弟彦とオグナは美濃の村の人々に混じって久礼波の作業を手伝うのが好きだった。
子供のことゆえ、たいした労働力になるわけではないが、自分の力で運べる大きさの石を運んだり、木切れを運んだり。そういうささやかな作業の積み重ねから、やがて立派な用水路が出来ていったりする。人々は喜ぶ。
「すごいねえ」
オグナなどは久礼波の知識と技術に心から感心し、感動していた。
そののめり込みようは弟彦以上で、さかんに久礼波に質問し、眼を輝かせてその作業を手伝っていた。

「久礼波はどこから来たの?」
オグナの無邪気な質問に、久礼波は少し困ったような笑みを浮かべた。
「海の向こうから、かな」
「家族の人、いないの?」
「いない」
「寂しくない?」
「ここへ来てからは寂しくないな」
「沙那女がいるから?」
「それもあるが、ここでの仕事はみんなが喜んでくれるだろ。
それがとても嬉しいから、寂しいのもどこかへいってしまうんだ」
「ふーん…」
「誰かのために働くことがこんなに満たされたものだとは思わなかったな」
「誰かって?」
「たくさんの人、ってことさ」
「オグナ、父上が呼んでたぞ。剣の稽古するんだろ」
弟彦が呼ぶとオグナは残念そうにその場を離れた。
オグナはまだ8才だが、生来のすばしこさや身軽さで、それなりに優れた剣の才能があるようだ。
弟彦ほどに弓の才があるわけではないと本人は諦めかけていたのだが、父は剣の才能の芽を見抜いた。
オグナもそれが嬉しかったのだろう。幼いながらも懸命に日々、父親と稽古に励んでいる。
作業が一段落して、今日も久礼波は沙那女と語り合っている。
いつしかこの二人は共に暮らすようになっていた。
少女のような、どこか少し寂し気な風情を漂わせた沙那女。
けれども久礼波といる時の沙那女は頬を上気させて楽し気に微笑んでいる。
ぼんやりと二人を見ていた弟彦は、幼い頃に亡くなった母とどこか沙那女は似ている、と思っていた。
はっきりと思い出せるほどに鮮やかな母の記憶ではなかったが。
「また見てる」
突然声をかけたのは麻多烏(またお)だった。
ひとつ年上でしかないこの幼馴染みの少女はやたらと姉さんぶって弟彦やオグナの世話を焼きたがる。
そのくせ大人の前ではわざとそっけないふりをしてみせたりする。
ころころ変わる態度が弟彦には解せない。
「ぼーっとしちゃって、みっともないったら」
「…っるせーな!」
清彦もこんなやつのどこが気に入っているのだろう。
自分にとっては兄のような従兄の好みも弟彦には理解出来ない。
-------------
静かに穏やかな日々は過ぎる。久礼波が美濃の住人になって2年あまりの年月が流れていた。
大和の五十瓊敷命(いにしきのみこと)が亡くなり、その墳墓の造営のために各地の人足が徴用された。
弟彦は14になった。オグナは十。それぞれに武芸に関しては天賦の才能を現すようになっていた。
もっともオグナはまだ幼いので、体格からしても膂力からしても大人にかなわない部分があるのはどうしようもなかったが。
弟彦の弓の腕はすでに大人の誰にも負けなかった。
父が浮かない顔をしている。大和からの使者が訪れたからだ。
日代大王(ひしろのおおきみ)の耳に美濃の美人姉妹の噂が届いたらしい。
后として召す、という。弟媛(おとひめ)はこの申し出を拒んだが、姉の八坂入媛(やさかいりひめ)は喜んで承諾した。
姉妹の家族も願ってもないことだと喜んでいる。
そのために日代宮から迎えが来るらしい。
この地の首長である父がもてなしのために頭を抱えているのかと思えば、どうもそれだけではないらしい。
「近々、大和の使者が来る。宴を開かねばならないが、弟彦、その使者が滞在する間はオグナを表に出すんじゃないぞ」
「…え、どうして?」
「杞憂に終わればいいが…」
父は理由を教えてはくれなかった。
幾日もたたずして、大和の使者は訪れた。
宿禰(すくね)という壮年の男は大王の腹心であるらしい。
遠路はるばる美濃まで来た、という機会に領地の見回りをして、整備された道や用水路、堤などを見咎めた。
「これを指揮したのは誰か?」
という問いに、人々は久礼波の名を挙げたが、宿禰は眉を上げた。
宿禰の命で久礼波は兵士達に無理矢理にその場に引きずり出された。
「汝(いまし)、こんなところにおったとは…」
弟彦の父はもちろんのこと、美濃の人々はそこで初めて久礼波の素性を知った。
彼はもともと大和に招聘された技術者だったのだ。
珠城大王の墳墓の造営のため、と。
死後にも権力を誇示するための巨大な墓が必要か。
久礼波にはそれがとても空しい行為に思えた。
自分の力は生ある人々の役に立てたい、と願う彼にとってその使命は辛かった。
そうして彼は大和から逃げたのだ。
「このまま戻ればよし。逃亡の罪は見逃そうと大王はおっしゃるだろう。汝の腕は必要だ。
従わなければ相応の咎があるだろう」
久礼波は沙那女のことを思った。
「その仕事が終われば、自由にしていただけますか」
「そのようにとりなそう。大王は心の広い方ゆえ」
「…ならば、参ります」
久礼波は眼を閉じた。その時。
「久礼波!行ってしまうの?」
飛び出してきたのはオグナだった。
宿禰の視線がふいに飛び出した子供の胸元に止まった。
「その勾玉…覚えがある。倭媛さまの持ち物だった。神宝でもある。それをなぜ汝が持つ?」
その勾玉はオグナが生まれた時から片時も離さず身につけてきた御統(みすまる) の首飾りで鈍い輝きを放ってきたものだ。
弟彦は血の気の失せた父の顔を見た。
------------

運命は音を立てて流れようとしていた。
------------
宿禰から、そして父親から語られたオグナの出生の秘密はにわかには信じがたいものだった。
オグナは日代大王の息子、兄、大碓王子(おおうすのみこ)と共に同時に生まれた双児の弟だという。
不吉な予言がなされ、そのために捨てられ、野に果てようとしたところを叔母の倭媛が救い出し、かねてより懇意だった弟彦の父に預けた子供だった。
弟彦の実の弟として育てられ、弟彦もオグナ本人も疑ってもみなかった。
真実を知っていたのはごく限られた大人だけだった。
「生きておられたとは。是非とも大王にお知らせせねばなりませんね」
オグナは蒼白な顔で弟彦の背中にしがみついて身を震わせていた。
宿禰からの知らせはただちに大和の大王のもとに届けられた。
后となる美姫のみならず、逃亡した技術者、死んだと思っていた弟王子まで見つかるとは、思いがけない大収穫に大王はたいそう気をよくしたらしい。
本来ならばそのままに捨ておいてもいいはずの王子だが、宿禰はオグナの才能を伝え、そのために大王は思惑を変えたらしい。
ただちに連れ帰れ、との命令もすぐさま帰ってきた。
オグナは泣いて拒否したが、命に従わねば弟彦の家族にもどういう咎めがあるやもわからぬ、と宿禰に言われ、従わざるをえなくなった。
弟彦は宿禰に噛み付いたが、たちまちに兵士達に取り押さえられ、唇を噛んだ。
いまだに大きな権力の前で、また大人達の前で非力な自分がひたすらに悔しかった。
久礼波も沙那女に別れを告げていた。
「仕事が終われば必ず帰る。だから待っていてくれ」
という久礼波の言葉に、涙でただ頷くしかない沙那女だった。
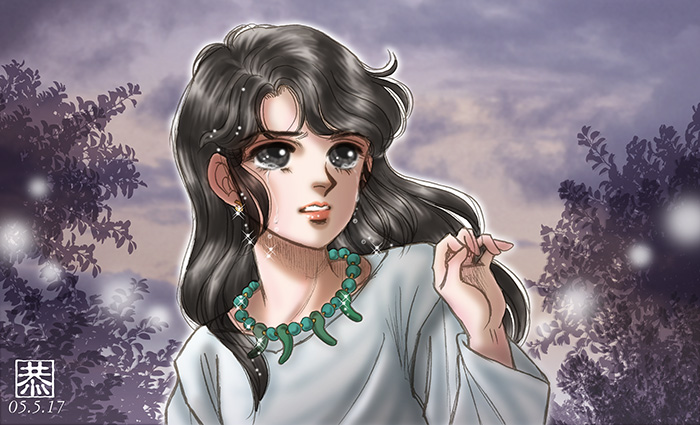
振り返り、振り返り、旅立って行ったオグナ。
弟彦はその姿が見えなくなるまで見つめ続けていた。
--------------

まほろば通信Gallery