まほろば通信Gallery


8 月魄(つきしろ)
その日以来、両道入媛は時折小碓を誘って山に出かけるようになった。この前に無駄にした収穫を取り戻すためばかりではなく、小碓は媛の眼差しが誰かを捜していることに気付いた。遠くに見かけた誉津別に媛は頭を下げた。誉津別は静かな笑みでそれに応えていた。
雪に閉ざされがちな真冬には媛はため息ばかりついていた。やがて訪れた春には少女のような華やいだ表情で、ただ初めは眼差しをかわすだけの誉津別との出会いが、やがて確実に距離が縮まっていくことがわかった。
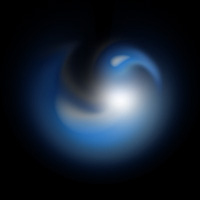
いつしか親し気に言葉をかわすようになった誉津別と両道入媛を見守る小碓も十三才になっていた。気付くと両道入媛の背丈を追いこしていた。七掬との勝負も三本に一本は勝てるようになった。しかしまだ腕力ではとても七掬にはかなわない。それが悔しくて、いまだに小碓は七掬の隙を伺ってしまう。
ある夕刻、重臣たちと語らっている七掬に足往がじゃれついた。その一瞬、背後に明らかに七掬の隙が生まれた。小碓はその瞬間を見逃すことなく、打ち込んだ。咄嗟にそれを受け止めそこねた七掬の太刀はしたたかに小碓の左腕を打っていた。
「あっ!」
腕に激痛が走り、小碓が蹲る。さすがに七掬も手加減を加える余裕がなかったらしい。七掬の木太刀は小碓の左腕の骨を折っていた。
その夜は少しばかり発熱したらしい。珍しく小碓は寝付いてしまった。添え木を当てて固定した左腕が痛んだ。
「なに、こういうものはすぐに治ります」
と手当てをした薬師は言った。七掬を責められない。背後から不意打ちしたのは自分の方なのだから。そのことで小碓は自己嫌悪に陥っていた。食事を持ってきてくれた両道入媛にも
「すみませんが叔母上、食欲がないんです…」
と告げたが、媛は
「ひとくちだけでも」
と勧める。せっかくの好意だと思うと、それ以上断れなかった。小碓は木の腕を膝にのせて、羹(あつもの)に口をつけた。それはさっぱりとした青菜とわずかな肉を入れただけの素朴なものだったが、予想外に美味だった。ほとんど初めて口にする美味に、思わず小碓は夢中になって平らげた。両道入媛は微笑みながらそれを眺めている。
「おいしかった!叔母上、驚きました、叔母上はこんなに料理が上手くていらしたのですね」
両道入媛はくすくす笑いながら告げる。
「私ではないのです、小碓。それは七掬があなたに食べさせてくれと持ってきたのです。自分で作ったらしいけど…」
「ええーっ!?」
驚愕のあまりに小碓は思わず空の腕を取り落とした。七掬にこんな特技があったなんて…。すぐには信じられない。いままでのつきあいの中で、大体七掬が笑ったのを一度も見たこともなかった。それなのに七掬がどういう顔をしてこういうものを作っているのかなんて、まったく想像も出来なかった。両道入媛は袖で口をおさえて笑い続けている。いずれにしても七掬が自分に気を遣っていてくれるのだということはよくわかった。

それから毎日のように届けられる七掬の食事のおかげか、若さゆえの回復力が幸いしたのか、腕は予想よりも早く完治した。
「すまなかった。…それと…どうもありがとう」
頬を染めて告げる小碓に、相変わらず七掬はにこりともしなかったが、ただ小碓の頭を二度ばかり軽く叩いた。