まほろば通信Gallery

4 七掬(ななつか)
翌朝、小碓が眼をさますと、館の外で昨日の犬が待っていた。
「あれ?足往(あゆき)…だったかな。迎えに来てくれたの?」
ついてこい、というように足往は軽く尻尾を振って背を向けた。
小碓が宮処の広場に出向くと、木太刀を持った七掬と憮然とした表情の大碓が待っていた。七掬が投げた木太刀の一本を小碓が受け止めると、七掬は
「私に隙があれば、いついかなる時でも打ちかかってこられよ」
と告げた。小碓は太刀を構えたが、確かに七掬に隙はなかった。攻めあぐねて逡巡していると、
「では私から参ろう」
と、七掬の太刀が振り降ろされた。咄嗟に受け止めた小碓の腕に痺れが走った。思わず木太刀を取り落としそうになる。七掬には相手が子供だとか、王子だとかいう理由で手加減する気などなさそうだ。今の受け太刀で小碓にはそれがわかった。しかし力の差はいかんともしがたい。どうしても応戦一方になってしまう。腕に力がなくなると、それすらも不可能になって、身をかわすことになってしまう。身軽さだけが小碓の武器のように思えた。そのままどれくらい対峙しただろうか。七掬の木太刀をかわしきれずに向こう脛に殴打を受けて小碓は転倒した。
「それでは大碓どのも」
七掬の指命で大碓がしぶしぶと剣を取る。今の小碓との対戦を見ていて、彼はすでに嫌気がさしていた。あきらかに小碓よりも彼の動きは鈍い。何度目かに大碓が地に倒れた時、稽古の様子を遠巻きに見守っていた女達から悲鳴が上がった。一人の女が飛び出してきた。大碓の乳母である由岐女(ゆきめ)だった。母親がわりに掌中の珠のように大切に育ててきた大碓が怪我をするのを由岐女は黙って見ていることが出来なくなった。なおも太刀を振るおうとする七掬の前に由岐女は毅然と立ちはだかった。
「七掬どのは厳しすぎます!」
由岐女に加勢するように侍女たちも叫ぶ。数人の女に口々に責められて、さすがの七掬もたじたじとなった。
「王子の怪我の手当てをしますからね!」
由岐女は言い放つと大碓を庇ってその場から立ち去った。
七掬は苦い顔のままで佇んでいる。少し気を取り直したように
「では小碓王子、もう一度」
と指名した。小碓には助け舟を出してくれるものなどいない。実は物陰から祈るように両道入媛が彼を見守っていたのだが、知るよしもなかった。疲れ果て、したたかに打たれた小碓が倒れて動けなくなった時、ようやく七掬は小碓を解放した。結局大碓はそのまま戻ってはこなかった。

その夜、小碓は一人きりの寝床で涙を流していた。打たれた身体中が痛む。七掬にしてみれば、それでも手加減はしていた。少なくとも骨折させないくらいには力を制御していた。しかし七掬の体躯から来る力は圧倒的だった。美濃で父が相手をしてくれていた時よりもはるかに容赦がない。体格と力の差はいかんともしがたいが、小碓にはそれが悔しくてならない。早く大きくなりたい、力が欲しい。
悔しさと痛みに耐えて眠って、また美濃の夢を見た。懐かしい家の気配。遠くに見える人影は弟彦か…。小碓はまた力の限りに弟彦を呼んだが、やはり声は届かないようだ。
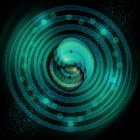
夜明け前、小碓は早くに起きだして、木太刀を手に取った。そしてそれを抱えたまま走り出した。どうすればいいのかわからない。けれども今日よりは明日、明日よりは明後日にもっともっと速く走れるようになりたい。七掬の太刀を受けても身じろぎもしないですむだけの力が欲しい。もっと強くなりたい。身体中に打撲の痛みが走るが、それ以上にはやる心にじっとしてはいられなかった。気がつくと走る小碓の側を足往が駆けていた。
「おまえもつきあってくれるのか?」
心強い味方が出来たような気がした。
その日から、小碓の早朝のひとり稽古が始まった。七掬の稽古を受ける前にかなりの距離を走る。さらに林の木々に縄で棒切れをいくつも結び付けてそれを打つ。打った木切れが返ってくるのを避けてさらに打つ。そんなふうにしてすっかり陽が昇るまでに自分のための訓練をするのだ。ただひたすらに身体を動かすことしか思いつかなかった。
(力が欲しい。強くなりたい)
という一心が小碓を駆り立てる。小碓の努力をおそらくは七掬も知っていたに違いない。毎朝早くに自分のもとから抜け出して行く足往をことさら咎め立てすることもしなかった。自分以外には決して慣れないこの犬が、ただ小碓だけに親しむのが不思議に思えてはいたのだが。

