まほろば通信Gallery


3 国見(くにみ)
小碓が大和に来てから一月ばかりの日が過ぎていた。
朝餉の席でふいに大王が小碓に問うた。
「小碓は馬に乗れるか?」
馬を所有しているのはごく一部の身分の高い人間だけだった。美濃にもほとんど馬はいなかった。しかし、美濃から大和に連れて来られる際に、なかば強引に乗せられた馬だったが、すぐにそれにも馴れ、大和に至る数日の間に乗りこなせるようになっていた。大王にそう返事をすると
「ならば今日は少し遠くまで出かけよう。ついて来るがいい」
と命じられた。
「父上、何処へ行かれます?」
「汝(いまし)も来るか、大碓」
「吾(あれ)は小碓と共には参りません」
この兄はなかなか小碓に馴染もうとしない。生まれてこのかた、ただ一人の日嗣皇子として我侭放題に育てられた大碓は自分よりもかなり下の方に弟を見下していた。頭から拒まれてしまうと小碓としても取りつくしまがない。なんとか仲良く、と望んでも兄が心を開いてくれない限りは空しい努力だった。

大王は小碓の他には2、3名の従者のみを従えて生駒の嶺を越えた。山頂で見渡す東にはやわらかな大和の山々があり、西の方角にはひろびろとした平野の向こうに煌めく海が見えた。大王は海を指し示す。小碓には初めて見る海だった。
「あの海の向こうには多くの国がある」
「熊襲(クマソ)とか蝦夷(エミシ)とか呼ばれる国ですか?」
「そればかりではない。肌や眼の色が違い、言葉も違う民が住む世界だ」
そんなふうな世界のことを小碓は想像したこともなかった。そういえば久礼波も海の向こうから来たと言っていた。けれども彼の顔だちも言葉も美濃や大和の人々と区別がつかないほど似ている。そうではなくて、もっと違う肌や眼の色をした人々が住む土地があるということなのだろうか。神々の世界とはまた違う世界なのだろうか。小碓が頭を悩ませていると大王は軽く笑った。
「その彼方の世界でも争いは絶えぬ。この大和とて決して安全とは言えぬ。海を越えて攻め入るものがあるとするならば、小碓、汝(いまし)はどうする」
「やはり戦わねばなりません…か?」
「そうだ。戦わねばならない。しかしそのためには多くの兵がいる。多くの武器も食料もいるぞ。国が豊かでなければ戦には勝てぬ。我が父祖たちは大和の地に正しく神を祀ってきた。それゆえに災厄も減り、稲も豊かに実った。しかし大和の周辺には我らと同じ神を祀ろうことを好まぬものもいる。同じ神を祀ることで心がひとつになる。しかしそれをしなければ国はまとまらず、従って豊かな兵力を持つことも出来ない。そういうところへ海の彼方から幾万の兵に攻め入られればどうなると思う」
「滅びて…しまうのでしょうか…」
「だから力が必要だ。心を同じくして戦う民が必要だ。そのためには我らに降ることを潔しとしない民も従わせねばならない。必要とあれば武力でもって」
武力で従わせるという行為がどういう意味を持つのかまだ小碓にはよくわからなかった。しかし、大王が自分に望んでいるのはそのための力でもあって、それゆえに自分は必要とされるということだけは理解出来た。そのことで自分がいるべき場所があるというのなら、もはや美濃へは戻れぬ今、父大王の意志に従うより他に道はないように思えた。少し心が重くなったような気がした。
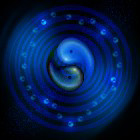
小碓と大王たちが宮に帰り着いた時には、すでに西の空が紅く染まり始めていた。馬から降りた小碓は宮の庭園内を歩いている一匹の犬を見つけた。それは小碓の肩ほどもある大きな犬で、長めの毛皮と金色に光る眼を持っていた。狼の血が入っているのかもしれない。しかし、生来動物好きである小碓はためらいなくその犬に近付いて手を差し伸べた。
「やめたほうがいい。そいつは人には慣れない」
突然の声に振り返った小碓の背後に一人の男が立っていた。父大王と同じくらいの年頃だろうか。大層背が高く、がっしりと鍛えた身体をしていて、さらに額に残る傷跡がその男の印象を険しいものにしているように見えた。

「おお、七掬。よいところへ参った。汝(いまし)の腕を見込んで頼もう。小碓に剣を教えてやってくれ」
大王が頼むくらいだから、七掬と呼ばれたその男はよほどの腕なのだろうか。小碓が改めてその男を見つめた時、大碓が父を迎えに現われた。
「そうだな。大碓も共に習うがいいぞ」
いきなりの父の提案に大碓ははっきりと不機嫌になった。
「吾はいまさら稽古など…」
と言いかける大碓も父の厳しい目線にぶつかって、しぶしぶながらそれを承諾しなければならなかった。
「儂は間もなく熊襲へ発つゆえにな。息子達を頼むぞ」
七掬は短く、承知しました、と答えた。
「この男は無愛想だが腕は立つ。小碓、期待しておるぞ」
言い残して去った大王を見送って立ち尽くす小碓のそばに先ほどの犬がじっと座っていた。小碓がそれに気付くと、犬は伸ばした小碓の掌をぺろりと舐めた。それを見た七掬はわずかに驚いたようだ。
「では王子、明日より始めましょう」
七掬は言って、犬を呼んだ。
「来い、足往(あゆき)」
犬は尻尾を振って彼に従う。それを見送った小碓は呆然としていた。
