まほろば通信Gallery


2 倭媛(やまとひめ)
やはり最も小碓に心を砕いてくれたのは倭媛だった。
「あなたを美濃に託したのは私です」
倭媛はそう告げた。
「あなたの母ぎみは、あなたの誕生をそれは心待ちにしていらしたから…。けれども亡き大巫女さまの予言を恐れるものは少なくなかったのです。でも私はどうしてもあなたを死なせたくはなくて…」
自分の出生の秘密と経緯については美濃から大和へ至る道すがら、宿禰からおおよそのことは聞かされていた。初めから自分は邪魔者なのだ、という思いで小碓の胸は痛んだが、倭媛の言葉でいくらか救われる気がした。そういう自分でも母は心待ちにしていてくれたのだ。見たこともない母の面影は、しかし、頭の中に具体的な像を結んではくれなかった。
「出来ることならばあのまま美濃で静かな日々を送らせてあげたかった。その御統(みすまる)の勾玉がまさか誰かの眼に触れることなどあるまいと思っていたので」
小碓は胸にかけた守護の御統を見つめた。神の留まります土地を捜して彷徨い歩いた日々。その長い旅の中で出逢った美濃の人々。倭媛は懇意になった美濃の人々に託すことで、哀しい宿命を背負った甥の別の人生を望んだのだった。その望みはもしかしたらこれからは空しくなってしまうかもしれない…。
「小碓、私はまもなく伊勢に参ります」
「え…?」
日の神がここと示した伊勢の土地に大規模な祀りどころを建築する工事は数年前から始まっていた。やがて完成間近のその地に倭媛は赴かねばならない。大王の、この大和の巫女として。この日代宮でただひとり、自分に親しんでくれる叔母に出会えたばかりなのに…。口に出さずに唇を噛んで俯く小碓の落胆が痛々しい。
「けれども小碓、私のかわりにこの媛と睦みなさい」
倭媛が声をかけると一人の若い女人が入ってきた。古風な形に結った髪と優し気な眼差し、初めてこの宮に来た時に微笑んでくれた女人だった。若くはあるが落ち着いた印象を受ける媛だった。
「両道入媛(ふたぢいりひめ)。大王の異母妹で、私と同じくあなたの叔母になります」
「よろしくね、小碓」
静かに微笑する両道入媛を見て、小碓は
(もしかしたらぼくの母もこういう人だったのだろうか…)
と、ふと思った。

数日後、心を残して倭媛は伊勢へ旅立った。
しかしその頃には小碓と両道入媛はすっかり打ち解けていた。問わず語りに両道入媛もまた早くに両親を亡くした身であること、それゆえに日代宮に引き取られたのだが、本当は生まれ故郷で静かに過ごしたかった、と語った。小碓とよく似た境遇ゆえに二人には共感するものが多かった。毎日のように宮処の中にあるお互いの館を行き来するようになった。相変わらず他の大人達はそういう二人を遠巻きに見ているだけだったが。
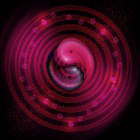
小碓は両道入媛から五十瓊敷命(いにしきのみこと)の陵墓建設の場所を聞き出し、そっと宮処を抜け出して、かつての美濃での友人とも言える久礼波(くれは)のもとを訪れた。
久礼波はいくらか疲れたような表情だったが、小碓を見つけると微笑した。
「久しぶりだな、オグナ。…いや、違ったな。いまはえーっと…小碓王子(おうすのみこ)だったか」
「オグナでもいいよ」
旧知の顔に出逢うとやはりほっとする。久礼波は咎めだてされることもなく、その技術を重用されて働いているようだ。そのことにも小碓は安堵した。同時に懐かしい顔を見るとたちまちに美濃のことが思い出される。父は、弟彦は、真若の叔母は、そして久礼波の想いびとの沙那女はどうしているのだろうか。美濃の話題に触れた時、久礼波は寂しそうな顔をした。
「もうよそう、オグナ。もはや帰れる場所ではないんだ」
自分に言い聞かせるように久礼波が漏らした一言に小碓はうなだれた。久礼波は小碓の髪をくしゃくしゃにすると、少し無理をしたかのように微笑んだ。
「ぼく…じゃなくて…あの…私はこれからも時々ここに来てもいいかな。もっと知りたいんだ。久礼波がしている仕事のこととか、大人になったらそういうことが出来るようになったら、きっとすごく嬉しいと思うし…」
半分は久礼波を励ますつもりでも、半分は小碓の本心だった。
「待ってるよ」
久礼波は今度こそ明るい笑みを浮かべた。

その夜、小碓は久しぶりに美濃の夢を見た。懐かしい家、懐かしい人々。父と、弟彦と暮らした家。光にあふれたその家に駆け込んでみても誰もいない。たったいままで人がいた気配はあるのに、呼んでみても誰も応えてはくれない。
「父上ー!弟彦ー!」
声の限りに叫んで、自分の声で眼が醒めた。涙が頬を伝っていた。
(もはや帰れる場所ではないんだ)
という久礼波の言葉がいつまでも耳の奥にこだましていた。

