まほろば通信Gallery


10 決意
両道入媛を乗せた輿と共に新羅の使者が大和を発ったのは、それから三日後のことだった。その一行を襲撃したものがある、という知らせが入ったのは一時ばかり後だ。
七掬がそれを聞いたのは小碓の館の中でだった。教わりたいことがある、という小碓の申し出で、珍しく館の中で小碓と対峙していたのだった。先ほどから落ち着かない小碓の様子を不審に思っていたところだ。日頃から仲がよかった媛が遠国に行ってしまう寂しさが、小碓を上の空にしていると推察していたのだが…。
七掬はただちにその場に向おうと、剣を手にして、立ち上がった。--瞬間、眼にも止まらぬ速さで小碓が彼の足下を掬い、思わず膝をついた時に取り落とした剣を小碓が素早く奪っていた。
「王子、なにを…」
七掬が言いかけた時には抜き身の刃が喉元に突き付けられていた。
明らかに迷いがない殺気が小碓の剣にはあった。
「行かせない。たとえ七掬でも…。いや、七掬だからこそ行かせない!」
日頃の稽古の時には思いもよらない、燃えるような眼差しが七掬を貫く。凛とした気魄に気押されて、七掬は言葉を失った。

瞬時に七掬の脳裏に二十年近くも昔の記憶が甦る。これと瓜二つの顔で、あの時、無頼の輩に絡まれて、額に傷を受けて倒れていた孤児の七掬を、刃との間に立ちはだかって救った少女。ちょうどこれくらいの年だった、稲日媛のことを。時がそのまま戻ったような気がした。あの時と同じだ。守るものがある時に、それほど鮮やかに毅然として強くなるのか…。それほどに守りたいものがあるということか…。二つの面影と時の記憶がぶれて重なり、目眩がした。喉元の刃はぴくりとも動かない。力が出ない…。七掬は完全に小碓に呑まれていた。
そうしていたのはさほど長い時間ではなかった。やがて、宮に駆け戻った兵士の声で、賊は討たれた、との報告があった。その声を聞いた小碓はたちまちに剣を取り落とし、崩れるように床に蹲った。顔を埋めているが肩が震えているのがわかった。
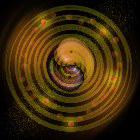
新羅の使者たちが宮に引き返してきたのはしばらくあとの事だった。大王は使者たちにわびを入れると、事の顛末を子細確認した。一行を襲ったのは誉津別王子であるという。
「誉津別が…いまだに生きておったのか。しかしあの男は狂人のはず。それがなにゆえ…。叛意があってのことか…?」
大王がつぶやいた時、半分正気をなくしたように項垂れた両道入媛が連れて来られた。小碓はたまらずに媛のもとに駆け寄って支える。媛のそばに付き従った侍女が震える声で大王に告げた。
「どうぞお許しを…媛さまは身籠っておられます…」
居並ぶ一同に衝撃が走った。
「よもや、あの男の子供か?!それゆえの襲撃か?狂人を装ったは偽りか?」
大王は媛に激しい視線を浴びせた。
「謀反人の子とあっては生かしてはおけぬぞ!」
大王がそう言い放った時、小碓は夢中で父の前に飛び出した。
「違います!それは私の…私の子供です!」
その場にいた人々にざわめきが伝わる。小碓はただ夢中だった。自分でも信じられないような言葉が喉からほとばしるような気がした。血を吐くような思いだった。
「父上にはお許しをいただかずに申し訳ありません。しかし私は叔母上を…両道入媛をずっと前から大切に思ってきました」
大王も重臣たちも言葉をなくしていた。まだ十四の、子供だとばかり思っていた王子が、そういうなりゆきで妻を娶るとは思いもよらなかった。しかし現にこの二人の仲の良さは宮に使えるすべての人間が日頃から眼にしていた様子だったし、あるいはそういうふうに男女の仲になっても不思議ではない、と思わせる経緯があった。大王は唸った。信じるべきだろうか。大王は七掬に問いかけた。
「儂よりも長いあいだ身近におる汝(いまし)にならわかるだろう。七掬、これはまことのことか?」
小碓は凍るような思いで立ち尽くしている。父の忠臣である七掬のことだ。さきほどの自分の行動から真実を見抜いているに違いない。七掬が否定すればすべてが終わってしまう。誉津別の死も、媛の中に宿る子供の命も、そして自分の存在も。小碓は眼を閉じた。心の中で誉津別に詫びた。
(私の力が足らずに…申し訳ありません…)
「まことのことでございます」
七掬の一言に小碓は弾かれるように眼を開けた。
「おふたりが公にされない間は、先に私の口から申し上げることが出来ませんでした」
七掬ははっきりと返答した。
大王は一応は納得したようだ。あるいは万一真実でなかったとしても、手許にある命ならば、いつでもなんとでも出来る、と思ったのかもしれない。小碓自身の命のように。
「二人の婚姻を許す」
大王はその場にいた者達に宣言した。新羅の使者には両道入媛のかわりに自ら志願した妥女(うねめ)が託された。誉津別の暴挙は悪しき凶神(まがかみ)に憑かれたゆえのものとされ、先の大王の王子として、丁重に葬られることとなった。ここに佐保の民の悲願は永遠に潰えた。
