まほろば通信Gallery


9 前夜
誉津別と両道入媛の語らいが親密さを増すにつれ、小碓はなにかと理由をつけては二人の側から離れるようになった。どう考えても自分が二人の邪魔をしているような気がしてならない。帰りがけには来るから、と足往を連れて山を歩く。
「小碓、私はあなたに気を遣わせているわね…」
両道入媛は申し訳なさそうに言うのだが、自分と共に出掛けないと彼女の自由は束縛されてしまう。少女のように華やいで幸せそうな媛のために、それくらいのことは少しも苦ではなかった。
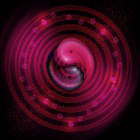
木の上で小碓はしばしまどろんでいた。足往が吠えて危険を知らせるまで目覚めないこともある。足往に吠えられて気がつくと、あやうく平衡が崩れて滑り落ちる寸前だったりもする。
このところあまりよく眠れない。初めの頃はただ見つめるだけで、言葉をかわすことがなくても、夢で少女に会えるだけで幸せだった。暖かい想いに胸が満たされて目覚めることが出来た。それなのにこのごろはそれだけでは満足出来なくなっている。逢いたい、触れたい、と思う。少女のことは大切に守り続けておきたい珠玉のような存在なのに、幻に少女の白い肌を見てしまう。背筋を貫くような凶暴な衝動が小碓を苦しめる。たとえ夢の中であっても、ひどく少女を涜すような罪悪感に襲われるのだ。それを怖れて眠れぬ夜が増える。
実は日代宮にも密かに小碓に想いを寄せる若い娘も少なくなかったのだが、小碓はそういう視線にはまったく気付かなかった。彼の心に存在する女人といえば、あの少女のみだった。
(…苦しい…)
悩む夜にふと思い出すのは弟彦のことだ。自分よりも四才年上の弟彦は、あるいはすでに妻を迎え、子供を設けたかもしれない。それであってもおかしくない。けれどもそういう悩みを相談出来そうな相手といえば弟彦くらいしか思いつかないのだ。無性に弟彦と語り合いたいと思う。いつしか小碓は十四才になっていた。

その夏、日代宮に思いがない訪問者があった。はるばると海を越えて、新羅の国からの使者が到着したのだ。使者といっても彼の国の貴族の子弟が中心の訪問団だ。それもあくまでも友好的な関係を相手は求めている。彼等が携えてきた多くの宝物に日代大王はすっかり気をよくしたらしい。さらに親密な交流を結ぼうと望むのも無理はなかった。
そのような時に両道入媛は大王の呼び出しを受けた。
嫌な予感に胸を詰まらせた媛が大王のもとに赴くと、やはり非常な勅命が待っていた。新羅の王族との婚姻関係を結ぶために、媛に海の向こうへ嫁げというのだ。まったくの政略結婚。大王の性格を知らない媛ではなかった。けれども今はどうしてもその運命を受け入れる気持ちにはなれない。
「お許しください。私にはお慕いするかたがおります」
「誰だ、それは?」
言えない…。答えられるわけがない。すでにこの世にはいないのと同じ存在である、誉津別のことなど。媛は絶句する。
「なに、嫁いでしまえば自然と情は湧いてくるものよの。そもそも汝(いまし)がこの宮に引き取られたのもこういう時のためであったしな」
「…いや!…嫌です。…私はまいりません!」
「我侭は許さぬ。客人が帰路に発たれるまで、ゆっくりと考え直すがよい」
大王は両道入媛の幽閉を命じた。

小碓がその事実を知ったのはほんのわずか後のことだった。その朝は誉津別との約束の日で、そのために媛を迎えにいこうとして、小碓は警護の兵士達に引き止められた。媛が閉じ込められた館のまわりは数人の武装した兵達が警護している。小碓ひとりでどうこう出来る状況ではなかった。ともかく事実のみを誉津別に知らせる他はなかった。

誉津別は蒼白な顔で小碓の報告を聞いていた。そして長いあいだ沈黙していた。その静寂(しじま)が重い。いっそのこと、自分が大王に願い出て、媛を解放してもらえることは出来ないだろうか、と小碓はぽつりと口にした。
「それはならぬ、小碓。そなたはまだそういう反目をしてはならぬ」
誉津別は日代宮における小碓の微妙な立場を理解していた。存在そのものが災いと取られるような行動は、ただちに小碓の命の危険をも暗示する。小碓の逡巡を痛々し気に眺めていた誉津別は静かに語りかける。
「私はいままで自分を偽って生きてきた。…しかしいつかは本来のあるべき自分に戻りたいと願っていた。どうやらその時が来たようだ。新羅の使者はいつ発つ?」
小碓がその日取りを答えると、誉津別は頷き、そして小碓の肩に手を置いて、同じ目線で語りかけた。
「そなたにもいつかこういう時は来る。その時には迷うな。自分の本当の心を見失うな。心は本来は誰のものでもなくそなた自身のものだ」
優しく笑んで、誉津別は背を向けた。小碓には誉津別の心情が痛いほどに理解出来た。それなのに自分はなにも出来ずにいるなんて…。震える頬をいつしか涙が伝っていた。
「初めてそなたを見た時は、私の心そのものが鳥になって飛んできたのかと思ったぞ」
立ち去る誉津別の後ろ姿が涙で滲んだ。

