まほろば通信Gallery


序--- 夏嵐(なつあらし)
夕暮れと共に次第に厚くなる雲が湿気をはらんだ風を運んでくる。蒸し暑く木々を揺らす風は人々の戦きと不安を象徴するようでもある。
その夜、日代宮(ひしろのみや)は異様な不安の直中にあった。若き大王の寵愛の后の初めての出産が間近に迫っている。本来ならば喜ばしい出来事であるにも関わらず、その出産には不吉な予言がなされていた。
年老いた大巫女は告げていた。生まれてくるのは双児。さらにそのうちの一人の子はやがて大王に災いをもたらすものになろう、と。古来より双児は忌まれていた。ただ、双児として生まれたというだけでも異常なことのように思われていた時代のことだ。その上に大巫女の予言はさらに不吉な暗示だった。大王のみならず、宮内のすべての人間がその瞬間を待って、ひたすらに息を潜めていた。聞こえるものは産屋からのうめき声と、后を介助し、励ます数人の女たちのささやきのみ。それすらかき消すように雷鳴が近付いてくる。
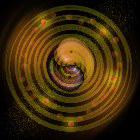
難産だった。ようやくの思いで子供をとりあげた老女が、抱き上げた子の産声を確かめた時、后の側の女が叫び声を上げた。
「媛さまが!…息をしていらっしゃいません!」
みどり児を他の女に手渡して、慌てて老女は稲日媛(いなびひめ)の側に寄り、蘇生のための処置を施した。しかし手当ても空しく、媛の呼吸は戻らない。哀れなことよ…、と老女は思った。しかし生まれてきたのは一人のみ。さすればこの子供が災いのもとであるとは思われぬ、と安心した部分もあった。赤児に産湯を使わせて浄めていた時、背後で悲鳴が上がった。すでに息絶えた媛の体内から、もうひとりの赤児が生まれてきたのだ。若い女は震えながらその赤児を抱きとめた。雷鳴にも負けぬ奇跡のように、その赤児はしっかりとした産声を上げた。

媛の死と生まれた二人の赤児のことはすぐさま日代大王(ひしろのおおきみ)のもとに伝えられた。后の死を悲しむ暇もなく、大王にはその媛の死そのものが不吉な赤児のせいのようにも思われた。息絶えた母から生まれてくるなど、いかにも普通とは思われぬ。やはりこのままにはしておけぬ。大王は宮に仕えるひとりの舎人を呼び、その赤児の始末を命じた。
吹き付ける強風と雨の中、時折稲光りに照らされる森を舎人(とねり)は赤児を抱いて走っていた。いかに大王の命であっても、生まれて間もない赤児を殺すのは忍びない。けれども命令に背くことは出来ない。迷いが舎人の足を遅らせる。荒い息をついて立ち止まった瞬間、なにものかに背後からしたたかに殴られて、彼はその場に昏倒した。

気がつくと、すでに夜明けが近いらしく、東の空が薄紅く染まっている。激しい雷雨も過ぎ去っていた。痛む頭を抱え、ふらつきながら立ち上がった舎人が見つけたのは血に染まった産着とかすかに残る獣の足跡。赤児の姿はどこにもない。自分を殴り倒したものの正体が知れないものの、赤児は狼にでも喰われたのかもしれない。いずれにしても自分がその子を直接手にかけずにはすんだのだ。彼はいささかの安堵を覚えつつ、獣に喰われた、と復命した。その証拠として差し出した血に染まった産着を見て、大王は納得した。

