平安王朝Gallery
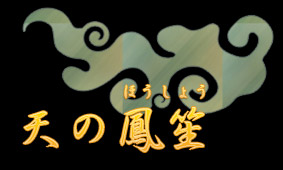
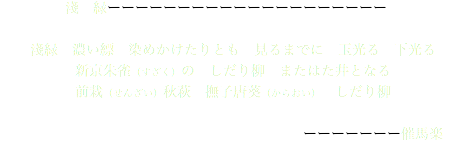


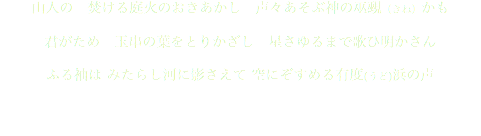
笙(しょう)ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
雅楽などで使う管楽器の1つ。フリーリード類に属する。
同様の楽器が東アジア各地に見られる。中国名・ション (Sheng)。
日本には奈良時代ごろに雅楽とともに伝わってきたと考えられている。
雅楽で用いられる笙は、その形を翼を立てて休んでいる鳳凰に見立てられ、
鳳笙(ほうしょう)とも呼ばれる。
匏(ふくべ)と呼ばれる部分の上に17本の細い竹管を円形に配置し、
竹管に空けられた指穴を押さえ、匏の横側に空けられた吹口より
息を吸ったり吐いたりして、17本のうち15本の竹管の下部に付けられた
金属製の簧(した:リード)を振動させて音を出す。
音程は簧の固有振動数によって決定し、竹管で共鳴させて発音する。
パイプオルガンの リード管と同じ原理である。
いくつかの竹管には屏上(びょうじょう)と呼ばれる長方形の穴があり、
共鳴管としての管長は全長ではなくこの穴で決まる。
その ため見かけの竹管の長さと音程の並びは一致しない。
屏上は表の場合と裏の場合があるが、表の場合は装飾が施されている。
指穴を押さえていない管で音が出な いのは、共鳴しない位置に指穴が
開けられているためである。
ハーモニカと異なり、吸っても吹いても同じ音が出せるので、
他の吹奏楽器のような息継ぎが不要であり、同じ音をずっと
鳴らし続けることも出来る(呼吸を替える時に瞬間的に音量が低下するのみ)。
押さえる穴の組み合わせを変えることで11種類の
合竹(あいたけ)と呼ばれる和音を出すことができる。
通常は基本の合竹による奏法が中心であるが、調子、音取、催馬楽、朗詠では
一竹(いっちく:単音で旋律を奏すること)や特殊な合竹も用いる。
その音色は天から差し込む光を表すといわれている。
Wikipediaより抜粋


なんだかこのごろずっと調子が良くないのですが、そのせいもあってか、
ちゃんとした花を描く気力が出ませんでした。
たまには花が出てこない作品もいいかなあ、ってことで楽器がテーマです。
雅楽でおなじみの「笙」ですね。鳳凰が翼をたたんだ形と言われているあたり
創作意欲をそそられる楽器でもあります。
なんだか私は無自覚にこういう楽器を描くのも好きなようです。
宇治、平等院の雲中供養菩薩像の写真集を手に入れまして、
いままでに未知の楽器が結構たくさんあるのを知りました。
ああいうものもまたモチーフに出来るかなあ?と考えております (^_^;)
鳳凰(白鳳)のカットは素材集からいただきました。もとが精密なeps画像だったので、
あえて加工することもなくそのままの使用ですが…。
epsゆえにかなり大きなサイズまで拡大が可能なので、やはり便利ですね。
背景の花の円形パターンは以前に描いていたものを初めて使いました。
これもepsなので使いやすかったですね。
Illustratorでの素材作りはそれなりに手間がかかりますが、質のいいものが出来るのは確かです。
また余裕がある時に作り溜めしておけばいいだろな、と思っております。